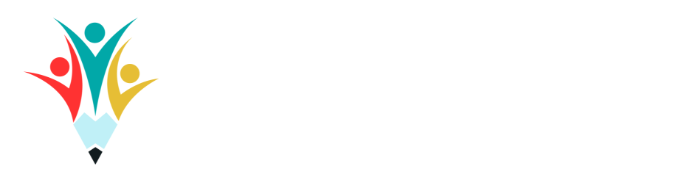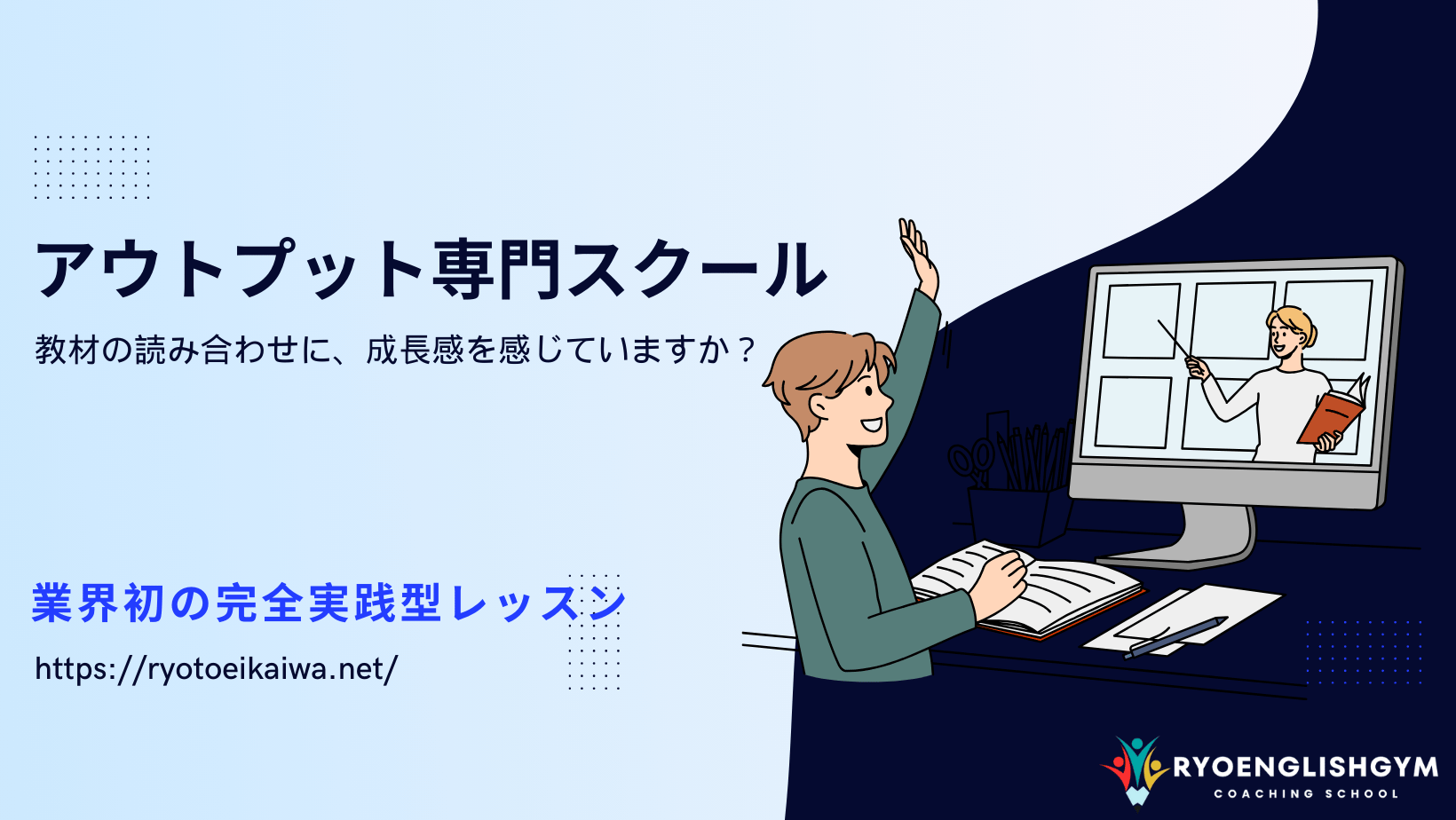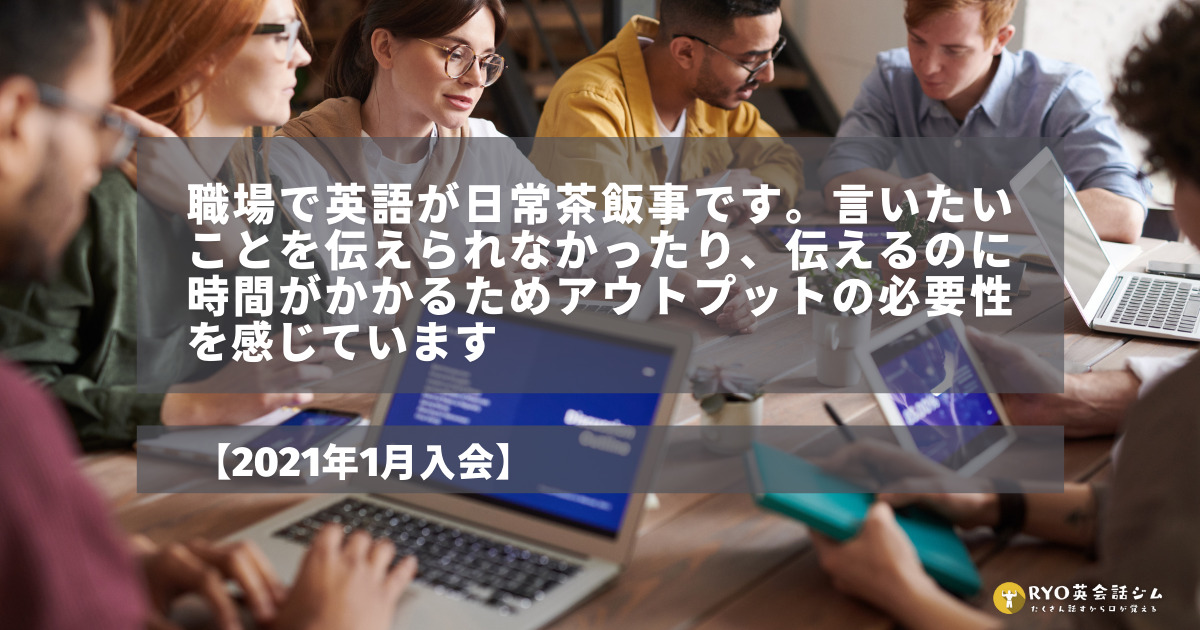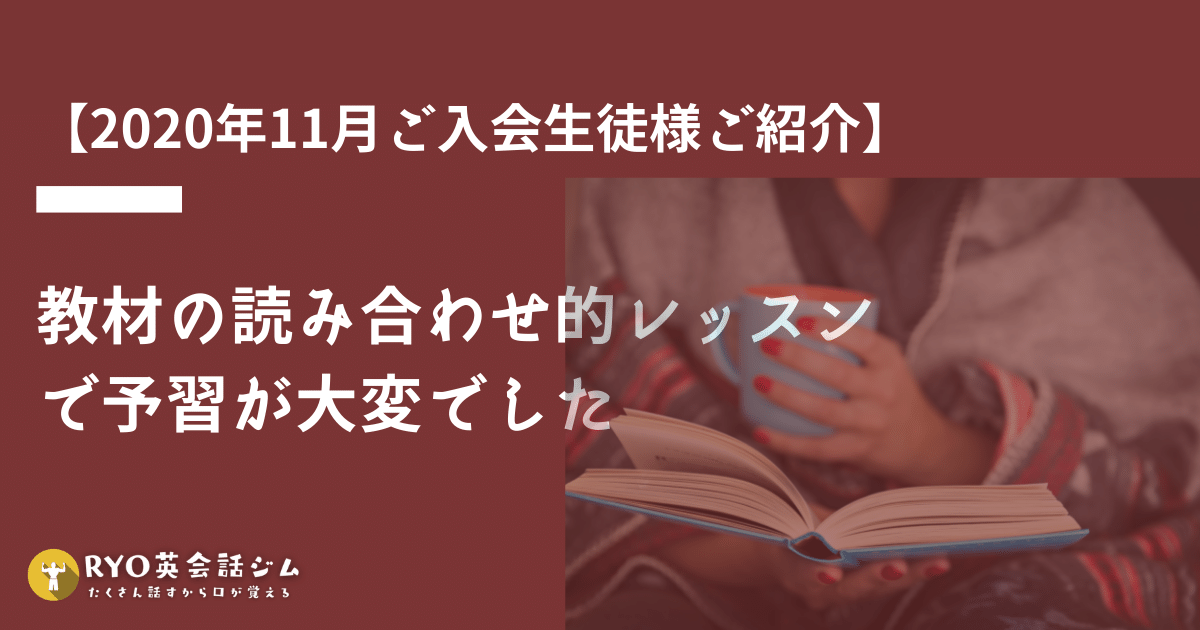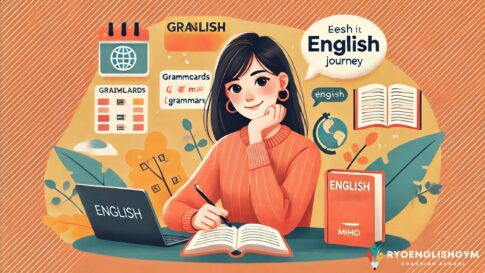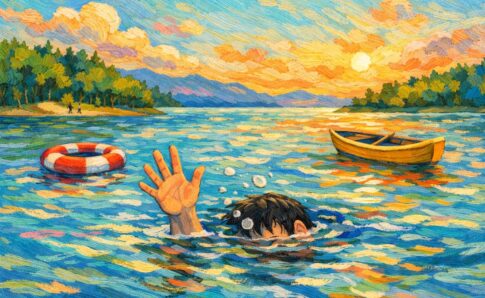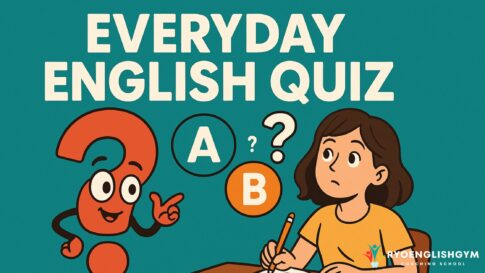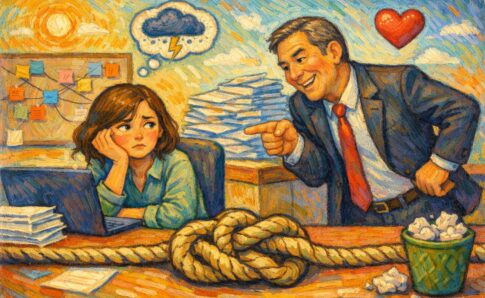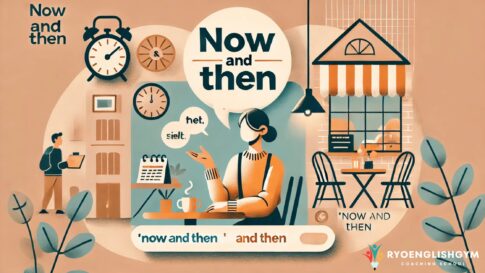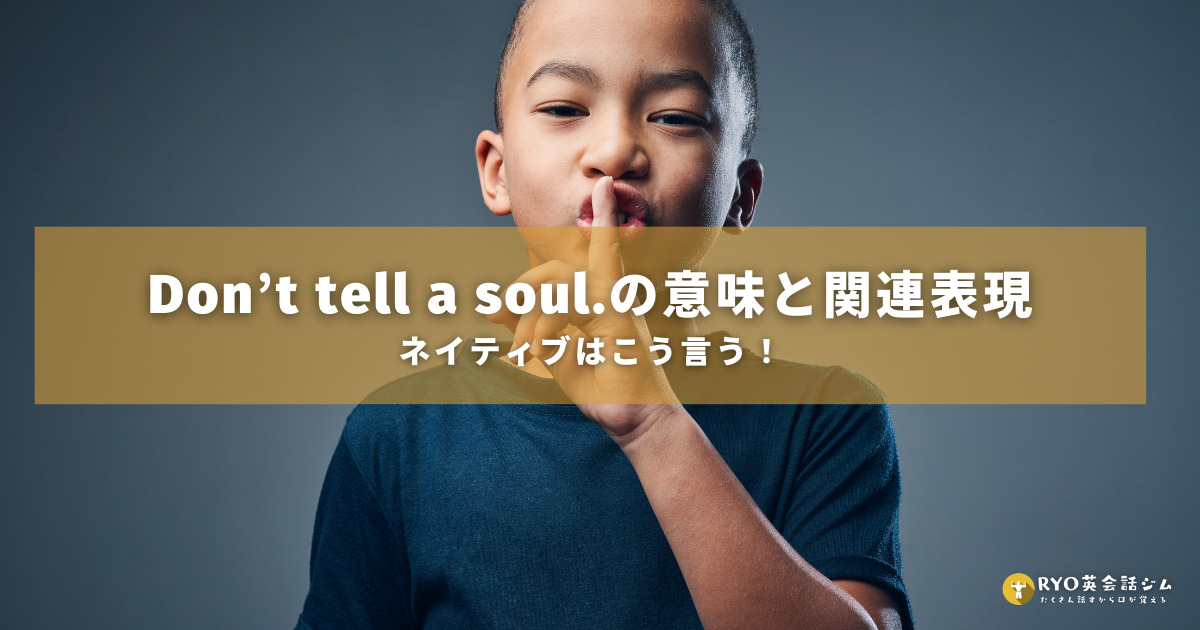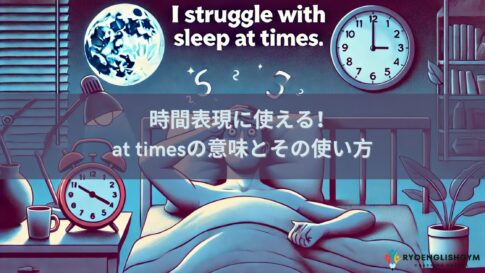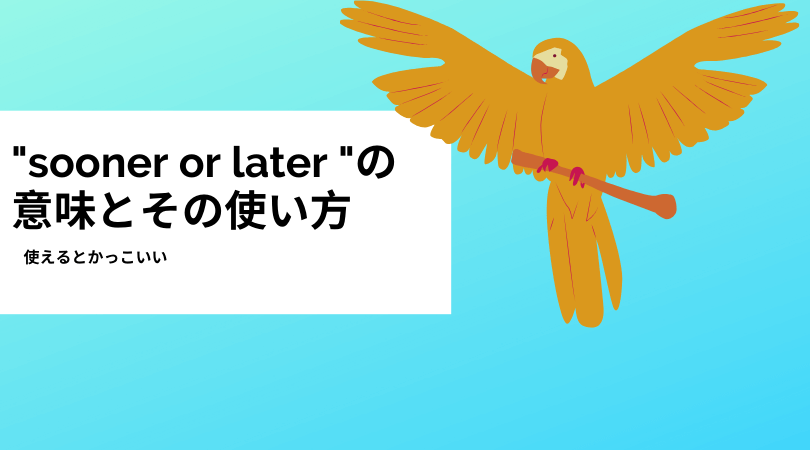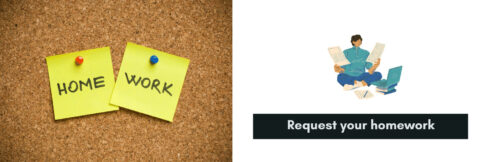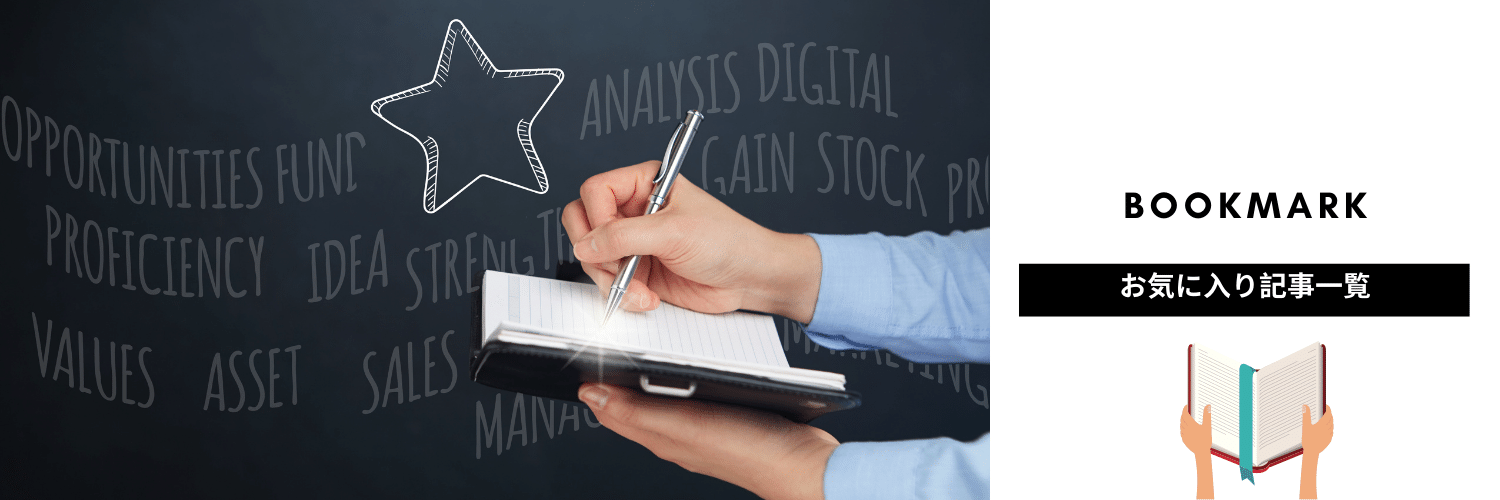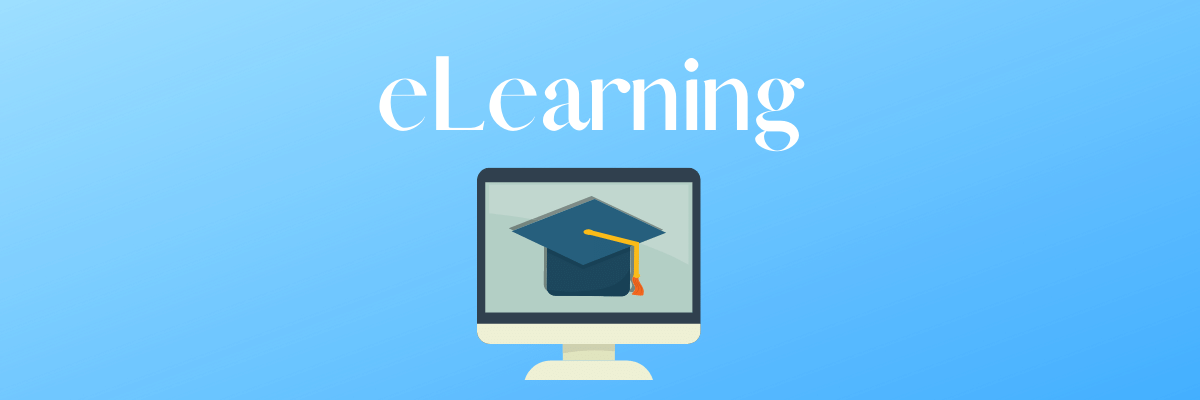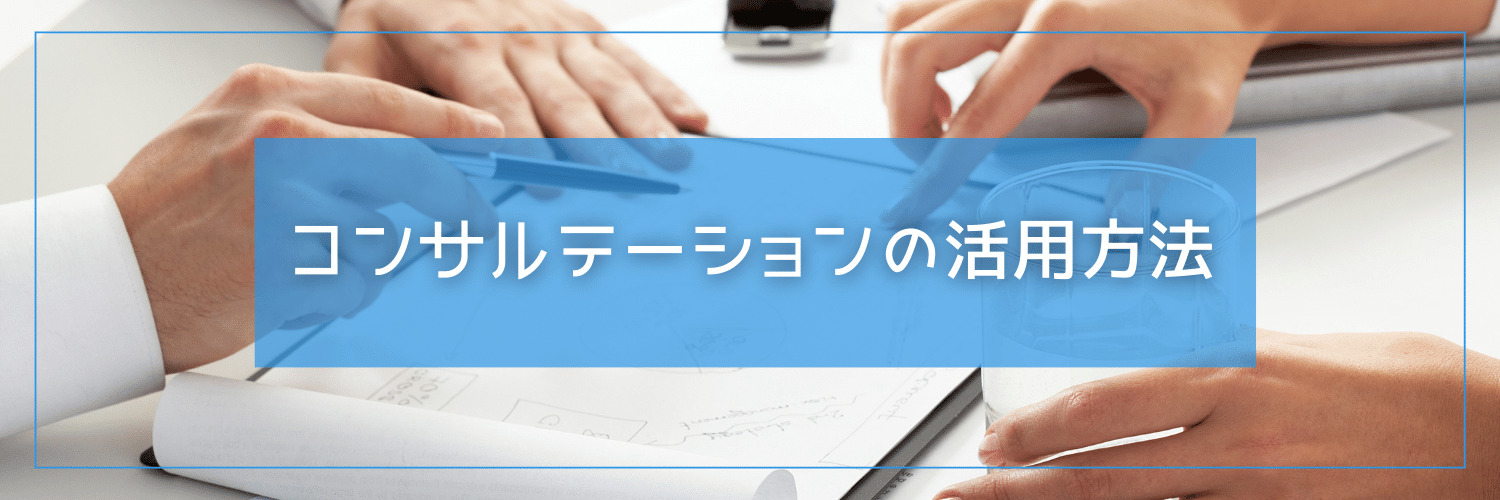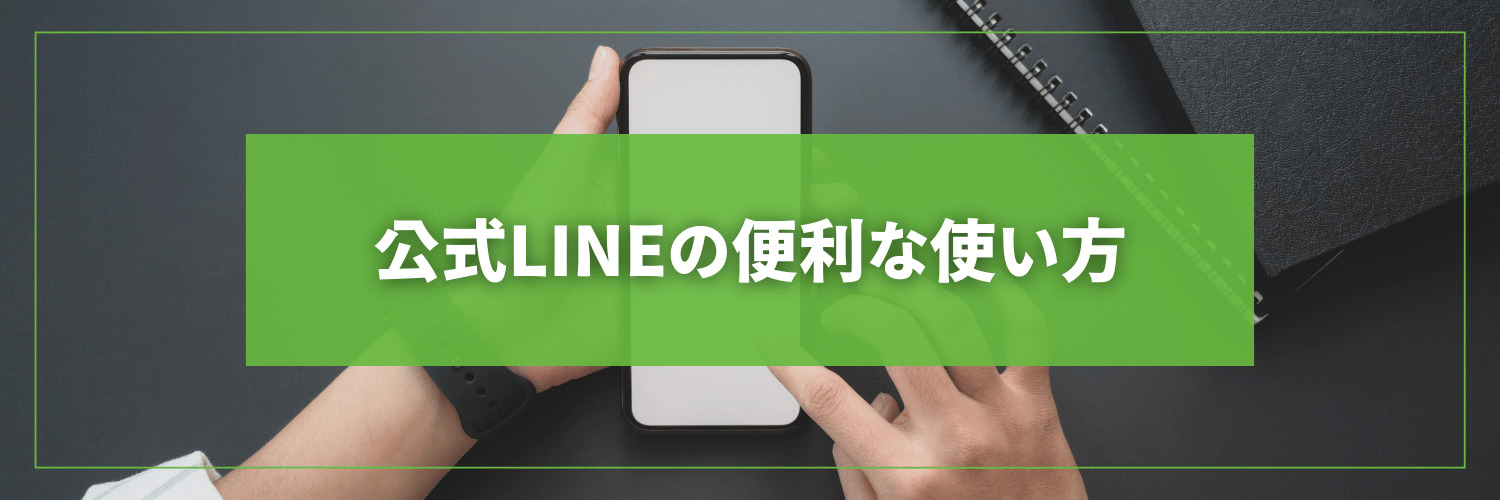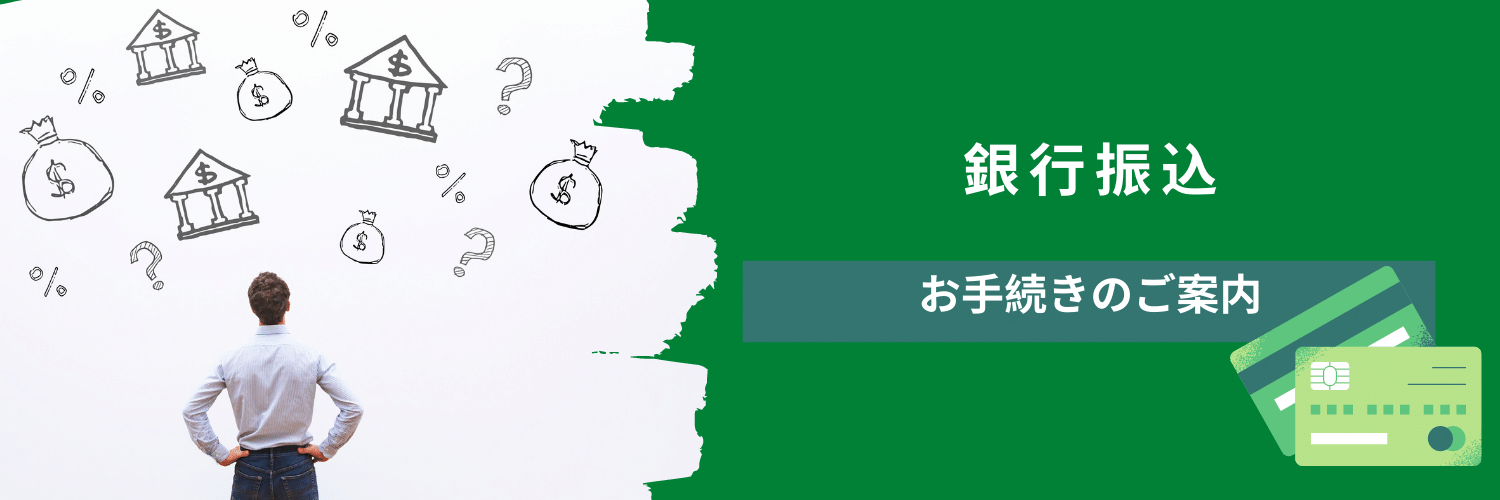こんにちは、RYO英会話ジムです。
「Dive in」は「さっそく始める」「勢いよく取り掛かる」という意味です。
直訳は「飛び込む」ですが、実際には 「早速やろう!」 という前向きなニュアンスで使われます。
✅ 例文:
- Let’s dive in!
→ さっそく始めよう! - The food looks great. Let’s dive in!
→ 美味しそう!いただきましょう!
このように、日常会話からビジネスまで幅広く使える便利なフレーズです。
それでは、「Dive in」の具体的な使い方をさらに詳しく見ていきましょう。
関連記事
英語の「始める」にもいろいろな表現があります。
特に “Let’s start” と “Let’s get started” は混同しやすいですが、それぞれのニュアンスには違いがあります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひあわせてご覧ください👇
👉 Let’s startとLet’s get startedの違いを徹底解説!使い分けのポイント
「Dive in」とあわせて読むと、シーンに応じた自然な言い出し方がよりクリアになりますよ。
- 1 僕の失敗談:「Dive in」を“diving”と勘違いした話
- 2 “Dive in”の意味とは?
- 3 “Dive in”の使い方
- 4 ポイントまとめ
- 5 シーン別英会話例
- 6 音声を聞いて練習しよう
- 7 アウトプットと改善を繰り返すことの大切さ
- 8 よくあるNG表現パターン
- 9 NGを避けるためのヒント
- 10 似た英語表現と関連語彙
- 11 自然に使い分けるコツ
- 12 練習クイズ
- 13 よくある質問(FAQ)
- 13.1 Q. “Dive in”とはどういう意味ですか?
- 13.2 Q. “Dive in”の使い方は?
- 13.3 Q. “Dive in”はフォーマルな表現ですか?
- 13.4 Q. “Dive in”と“Jump in”の違いは?
- 13.5 Q. “Dive in”と“Get started”の違いは?
- 13.6 Q. “Kick off”と“Dive in”はどう使い分けますか?
- 13.7 Q. “Dive in”の過去形は?
- 13.8 Q. 日本人が間違えやすい“Dive in”の使い方は?
- 13.9 Q. “Plunge into”や“Embark on”との違いは?
- 13.10 Q. 効率的に英語表現を覚えて実際に使えるようになるには?
- 14 まとめ
僕の失敗談:「Dive in」を“diving”と勘違いした話
「飛び込む」だけで覚えて混乱した経験
正直に言うと、僕自身も最初は 「Dive in=水に飛び込むこと」 だと思っていました。
ダイビング(diving)と結びつけて覚えてしまい、友達との会話で食事のシーンでも使えると知らずに混乱…。
そのせいで、「Dive in」を聞いたときに「え?今から泳ぐの?」と頭の中が一瞬真っ白になったことがあります。
読者への共感
きっと同じように、直訳で「飛び込む」とだけ覚えてしまう方も多いと思います。英語は「単語のイメージ」だけで覚えると、実際の会話で「なんか違う?」とつまずくことがよくあるんですよね。
克服のコツ(Tips)
僕がこの混乱を克服できたのは、「Dive in=勢いよく始める」と具体的なシーンに結びつけて覚え直したからです。
例えば、
- 仕事:Let’s dive in and start the project!(さっそく始めよう!)
- 食事:The food looks great. Let’s dive in!(美味しそう!いただきましょう!)
👉 ポイントは、「Dive in=始めよう!」と日本語の自然なフレーズに置き換えてイメージすること。
こうすると、もう「泳ぐ」イメージで迷うことはありませんでした。
📩 英語を話せるようになる第一歩として、リョウが無料で学習相談を実施中です。
発言内容の見える化や添削で、あなたの課題を明確にし、次の一歩を一緒に見つけましょう。
“Dive in”の意味とは?
「Dive in」は直訳すると「飛び込む」ですが、会話で使うときは 「さっそく始める」「勢いよく取り掛かる」 という意味になります。
カジュアルな日常会話でも、ビジネスシーンでもよく耳にするフレーズです。
“Dive in”の使い方
仕事やプロジェクトを始めるとき
- Let’s dive in and start the project!
(さっそくプロジェクトを始めましょう!)
新しいタスクや会議の冒頭で「よし、始めよう!」という前向きな雰囲気を作れます。
食事のシーンで
- The food looks amazing. Let’s dive in!
(料理が美味しそう!さっそくいただきましょう!)
食事を「楽しみにしていた気持ち」を表す場面でも自然に使えます。
新しい体験やチャレンジで
- I’m nervous, but I’m ready to dive in!
(ちょっと緊張するけど、挑戦する準備はできてるよ!)
「勇気を出して挑戦する」というニュアンスを伝えられます。
会議やディスカッションを始めるとき
- Shall we dive in?
(始めましょうか?)
フォーマルすぎず、スムーズに本題に入るときに便利です。
ポイントまとめ
- Dive in=「さっそく始める」「勢いよく取り掛かる」
- 日常会話(食事やチャレンジ)でも、ビジネスシーン(会議や仕事開始)でも使える
- 場を前向きにする効果がある
シーン別英会話例
1. 仕事・プロジェクト開始の場面
A: Are you ready to start the new project?
(新しいプロジェクトを始める準備できた?)
B: Yes, let’s dive in and see how it goes!
(うん、さっそく始めてみよう!)
👉 コツ:ビジネスでは「Let’s dive in」が、チーム全体のモチベーションを上げる効果があります。
2. 食事の場面
A: Wow, this looks delicious!
(わあ、美味しそうだね!)
B: Absolutely. Let’s dive in!
(ほんとだ!さっそくいただこう!)
👉 コツ:日本語の「いただきます」に近い感覚で、気軽に使えます。
3. 新しいチャレンジに挑戦するとき
A: I’ve never tried surfing before.
(サーフィンは初めてなんだ。)
B: Don’t worry, just dive in and have fun!
(大丈夫、思い切って飛び込んで楽しんでみて!)
👉 コツ:「勇気を出して挑戦する」というポジティブな雰囲気を伝えたいときに使えます。
4. 会議やディスカッションの開始
A: Shall we go over the agenda first?
(先に議題を確認しましょうか?)
B: Sure, then let’s dive in to the discussion.
(いいですね、それじゃあ本題に入りましょう。)
👉 コツ:会議での切り替えに便利。フォーマルすぎず、スムーズに本題へ移れるフレーズです。
まとめのポイント
- 「Dive in」=前向きにスタートする合図
- 場面は「仕事・食事・チャレンジ・会議」など幅広い
- 直訳で考えず、日本語の「さっそくやろう!」に置き換えて覚えると自然
音声を聞いて練習しよう
例文1: 仕事のスタート時
英語: Let’s dive in and start the project!
和訳: さっそくプロジェクトを始めましょう!
この例は、仕事やプロジェクトの開始時に使われるシーンです。特に、チームでの会話や、何か新しいタスクに取り掛かるときにピッタリです。「Dive in」を使うことで、積極的に物事を進める意思が伝わります。
例文2: 会話を進めるとき
英語: We’ve talked enough about the details, now let’s dive in!
和訳: 詳細については十分話したので、そろそろ本題に入りましょう!
この例では、前置きが長くなったときに、さっと本題に入る流れを作りたい場面で使います。「Dive in」を使うことで、会話を前に進めたい意図が伝わり、スムーズに次のステップに移ることができます。
例文3: 食事のシーンで
英語: The food looks amazing! Let’s dive in!
和訳: 料理が美味しそう!さっそくいただきましょう!
この例は、料理が目の前に出されたときに使う表現です。食事を楽しみにしている気持ちが伝わり、場の雰囲気を明るくする効果があります。
例文4: 新しいチャレンジに取り掛かるとき
英語: I’ve never tried rock climbing before, but I’m ready to dive in!
和訳: ロッククライミングは初めてだけど、挑戦する準備はできてるよ!
新しいことに挑戦する場面で、「Dive in」を使うことで、前向きな姿勢や勇気を表現できます。初めての経験に対して積極的に向き合う気持ちが伝わる表現です。
アウトプットと改善を繰り返すことの大切さ
英語を学んでいると、「単語やフレーズを覚えたのに、いざ話すと出てこない」「間違うのが怖くて黙ってしまう」と感じることはありませんか?
実はここで大事なのが、間違えてもいいからアウトプットする → その場で改善する → 自信につなげる というサイクルです。
RYO英会話ジムでは、まさにこのサイクルを徹底しています。レッスン内で自分の発言が可視化され、講師からすぐにフィードバックをもらえる仕組みがあるので、「言いたいことが言えないもどかしさ」から解放されやすいのが特徴です。
実際に、ある受講生の方からはこんな声をいただきました。
- 「会議で黙ってしまうことが多かったけど、トレーニングを重ねて“間違えても発言していいんだ”と思えるようになりました」
- 「以前は“勉強しているのに話せない”と悩んでいましたが、アウトプットの量と改善の質が変わって、自分でも驚くほど言葉が出てくるようになりました」
英語は頭で理解するだけでは伸びにくく、声に出して間違いを直すことで初めて“使える力”になっていきます。
「もっと自然に話せるようになりたい」「会議や雑談で自信を持って発言できるようになりたい」——そんな方は、ぜひ一度体験してみてください。
※実際の受講生の成果・声をもっと見たい方は 👉 こちら からどうぞ。
よくあるNG表現パターン
1. 不自然な言い回し
例:I will dive in to the pool of this project.
(直訳で「このプロジェクトのプールに飛び込みます」)
👉 日本語の「飛び込む」に引っ張られて、比喩をそのまま拡張してしまうミスです。英語では「Dive in」はそれだけで「取り掛かる」という意味になるので、余計な言葉を足すと不自然になります。
2. 間違った場面での使用
例:I dive in to the meeting late.
(「会議に遅れて飛び込む」というつもりで使った)
👉 「Dive in」は 「勢いよく始める」や「取り掛かる」 というニュアンスなので、遅刻して会議に駆け込むような場面には不向きです。
この場合は I rushed into the meeting や I joined the meeting late の方が自然です。
3. 文法ミス(過去形の誤り)
例:Yesterday, I dived in to the new task. ×
👉 多くの学習者が「Dive in」の過去形に迷います。
正しくは:
- dove in(米国英語でよく使われる)
- dived in(イギリス英語で一般的)
どちらも正解ですが、アメリカ英語に慣れている人は dove in を自然に使うケースが多いです。
NGを避けるためのヒント
- 直訳で考えない:「Dive in=飛び込む」ではなく「勢いよく始める」と覚える。
- 場面をイメージする:プロジェクト開始、食事、挑戦、本題に入るシーンなど。
- 文法に注意:過去形は「dove」か「dived」でOK。
似た英語表現と関連語彙
1. Jump in(急に加わる・割り込むイメージ)
意味:「途中から参加する」「気軽に入る」というニュアンス。
コツ:Dive inよりカジュアルで、会話の流れに途中参加するときに使うと自然。
会話例
A: If you have any suggestions, feel free to jump in anytime.
(提案があれば、遠慮せずに途中で言ってね。)
B: Thanks, I’ll jump in if I think of something.
(ありがとう、思いついたら割り込むよ。)
2. Get started(始める)
意味:もっともシンプルで一般的な「始める」。
コツ:勢いや感情は含まれず、淡々と始めるニュアンス。フォーマルでもOK。
会話例
A: Should we get started with the presentation?
(プレゼンを始めましょうか?)
B: Yes, let’s get started.
(はい、始めましょう。)
3. Kick off(始める・開始する)
意味:イベントや会議の「開始」を意味し、ややフォーマル。スポーツのキックオフが語源。
コツ:会議や公式イベントで「スタートの合図」として使うと自然。
会話例
A: We’ll kick off the meeting at 10 a.m.
(会議は午前10時に始めます。)
B: Great, I’ll be ready.
(了解です、準備しておきます。)
4. Plunge into(思い切って取り組む)
意味:「飛び込む」ニュアンスはDive inに近いが、より真剣・深く取り組むイメージ。
コツ:学習や研究など、集中して取り掛かる場面で使うと自然。
会話例
A: She plunged into her studies for the exam.
(彼女は試験勉強に没頭した。)
B: That’s the spirit!
(その意気だね!)
5. Embark on(取り組みを開始する)
意味:少しフォーマルで、「新しいプロジェクトや旅に取り組む」を表す。
コツ:ビジネス文書やスピーチでよく使われる。
会話例
A: We are about to embark on a new project.
(新しいプロジェクトに取り組もうとしています。)
B: Sounds exciting, good luck!
(ワクワクしますね、頑張って!)
自然に使い分けるコツ
- Dive in:カジュアルに「勢いよく始めよう!」
- Jump in:気軽に「途中から加わる」
- Get started:ニュートラルに「始める」
- Kick off:会議やイベントの正式な「開始」
- Plunge into / Embark on:真剣に取り組む、フォーマルな「開始」
練習クイズ
問題1
会議をスムーズに始めたいときに自然なのはどれ?
a) Let’s dive in the pool.
b) Shall we dive in?
c) Let’s jump over.
- a) は直訳で「プールに飛び込みましょう」となり不自然。
- c) の「jump over」は「飛び越える」という意味で会議には不適切。
- b) の「Shall we dive in?」が自然で、「始めましょうか?」という流れを作れる。
問題2
「もしアイデアがあれば、途中で遠慮なく発言してね」と言いたいときは?
a) Feel free to jump in anytime.
b) Feel free to dive in anytime.
c) Feel free to get started anytime.
- Jump in は「途中参加・割り込む」というニュアンスで議論の途中で使える。
- Dive in は「勢いよく始める」で、ここでは不自然。
- Get started は「始める」で、文脈に合わない。
問題3
「10時に会議を開始します」とフォーマルに伝えたいときに適切なのは?
a) We’ll kick off the meeting at 10 a.m.
b) We’ll dive in the meeting at 10 a.m.
c) We’ll plunge into the meeting at 10 a.m.
- Kick off は「会議やイベントを開始する」というフォーマルな表現。
- Dive in はカジュアルで「勢いよく始める」ニュアンスなので公式アナウンスには不向き。
- Plunge into は「没頭する」という意味で会議開始には合わない。
問題4
「彼女は試験勉強に没頭した」と言いたいときに自然なのは?
a) She dove in her studies for the exam.
b) She plunged into her studies for the exam.
c) She kicked off her studies for the exam.
- Plunge into は「熱心に取り組む・没頭する」に自然。
- a) の dove in は「勢いよく始める」なので少し軽すぎる。
- c) の kick off は会議やイベントの開始で使うのが自然。
問題5
「私たちは新しいプロジェクトに取り組もうとしています」と言いたいときは?
a) We are about to embark on a new project.
b) We are about to dive in a new project.
c) We are about to jump on a new project.
- Embark on は「新しいことに取り組む(特にプロジェクトや旅)」で自然。
- b) の dive in a project も意味は通じるがややカジュアル。
- c) の jump on は「飛び乗る」という意味で不自然。
よくある質問(FAQ)
Q. “Dive in”とはどういう意味ですか?
A. “Dive in” は直訳すると「飛び込む」ですが、実際の会話では 「さっそく始める」「勢いよく取り掛かる」 という意味で使われます。食事や仕事、会議など、前向きに始めたいときによく使う表現です。
Q. “Dive in”の使い方は?
A. “Dive in” はシンプルに「始めよう!」というニュアンスで使えます。例えば Let’s dive in!(さっそく始めよう!) や Shall we dive in?(始めましょうか?) のように、友人同士の会話からビジネスまで幅広く使えます。
Q. “Dive in”はフォーマルな表現ですか?
A. “Dive in” はどちらかというと カジュアル寄り です。ただし、会議の冒頭などでも「では始めましょう」の意味で使われるので、日常会話からビジネスシーンまで柔軟に対応できます。
Q. “Dive in”と“Jump in”の違いは?
A. “Dive in” は「勢いよく始める」というニュアンス、“Jump in” は「途中から参加する」「気軽に加わる」というニュアンスです。会議中に「意見があれば遠慮なく言ってね」と言うときは Jump in が自然です。
Q. “Dive in”と“Get started”の違いは?
A. “Get started” はシンプルに「始める」という意味で、ニュートラルかつフォーマルな表現です。一方で “Dive in” は「勢いよく」「ためらわずに」という前向きなニュアンスが含まれます。
Q. “Kick off”と“Dive in”はどう使い分けますか?
A. Kick off は会議やイベントの「開始」を表すフォーマルな表現です。Dive in はもっとカジュアルで、「さっそくやろう!」という雰囲気を出したいときに適しています。
Q. “Dive in”の過去形は?
A. “Dive in” の過去形は、アメリカ英語では dove in、イギリス英語では dived in が一般的です。どちらも正しいですが、アメリカでは dove in がよりよく使われます。
Q. 日本人が間違えやすい“Dive in”の使い方は?
A. よくある間違いは、直訳で 「プールに飛び込む」 というイメージで覚えてしまうことです。実際には「勢いよく始める」という意味なので、文脈に応じて自然に使うことが大切です。
Q. “Plunge into”や“Embark on”との違いは?
A. Plunge into は「没頭する」、Embark on は「新しいことに取り組む(特にプロジェクトや旅)」というフォーマルな表現です。Dive in はもっとカジュアルで、日常会話で気軽に使えるのが特徴です。
Q. 効率的に英語表現を覚えて実際に使えるようになるには?
A. 単語やフレーズを知るだけではなく、実際に声に出してアウトプットすることが重要です。間違えてもその場で直して改善できれば、一気に実力が伸びます。RYO英会話ジムでは、この「アウトプットと改善」のサイクルを徹底できる環境を提供しています。興味のある方は 無料体験レッスンをご覧ください。
まとめ
「Dive in」という表現は、日常会話からビジネスまで幅広く使える便利なフレーズです。直訳で「飛び込む」と覚えるよりも、「さっそく始める」「勢いよく取り掛かる」 とイメージした方が自然に使えます。
また、「Jump in」「Get started」「Kick off」など似た表現と比較することで、状況に合わせた言い回しも選べるようになります。よくあるNG表現や文法の誤りを避け、シーン別に実際の会話で使っていくことが大切です。
英語表現は「知っている」だけでは不十分で、実際に声に出してアウトプットし、間違いを改善していくことで初めて身につきます。
🎯 実際にアウトプットしてみたい方は ▶︎ RYO英会話ジムの無料体験レッスンで、「知ってる英語を、使える英語に」 変えていきましょう!